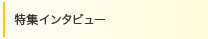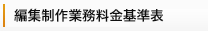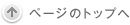2014年11月、新潮社から新雑誌『工芸青花(せいか)』が刊行された。A4のハードカバーで布張り、表紙に箔捺しという豪華な造本で、限定1200部発行、定価は8000円。骨董、茶の湯、西洋の中世美術、生活工芸等のテーマで、写真を大きく使っている。
これを立ち上げ編集長を務めるのは、『芸術新潮』やとんぼの本シリーズの編集を手がけてきた菅野康晴氏だ。
出版不況が深刻となる中、このような雑誌を創刊した理由、今後の出版や編集のあり方について、お話を伺った。
新潮社『工芸青花』編集長
菅野 康晴 氏 Yasuharu Sugano
1968年栃木県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。学生時代から美術や骨董に興味があり、『芸術新潮』や平凡社の『太陽』等を好んで読んでいた。こうしたグラフ誌に出てくる世界に触れることを仕事にしたいと、1993年新潮社に入社。『芸術新潮』編集部に15年間在籍、その後とんぼの本シリーズ編集部のヘッドを務め、美術・工芸・骨董のジャンルを中心に多くの企画を手がけた。
限定1200部、読者は順調に増加中
——まずは『工芸青花』について基本的なことを教えてください。
 年に3回発行する雑誌です。2014年11月刊の第1号は1000部、2号からは1200部限定で、全冊にシリアルナンバーを捺しています。定価は本体8000円。ただし年会費2万円で「青花の会」に入会していただくと、1年間3号分をお届けします。会員の定員は1000名で、少しずつですが増えていて、いまは800名程です。会員への送付分以外は、青花のサイト内のウェブショップと、各地の書店やギャラリーなど約40店舗でも販売しています。販売店に卸す場合は買切りでお願いしているのですが、ありがたいことに軒数も冊数も増えています。雑誌の内容は美術、工芸、骨董、建築など、私がこれまで仕事をしてきた分野が主です。出版だけでなく、そうした分野の催事(講座、茶会、演奏会など)や、オリジナル商品(器、絵葉書、アクセサリー)の物販も行なっています。
年に3回発行する雑誌です。2014年11月刊の第1号は1000部、2号からは1200部限定で、全冊にシリアルナンバーを捺しています。定価は本体8000円。ただし年会費2万円で「青花の会」に入会していただくと、1年間3号分をお届けします。会員の定員は1000名で、少しずつですが増えていて、いまは800名程です。会員への送付分以外は、青花のサイト内のウェブショップと、各地の書店やギャラリーなど約40店舗でも販売しています。販売店に卸す場合は買切りでお願いしているのですが、ありがたいことに軒数も冊数も増えています。雑誌の内容は美術、工芸、骨董、建築など、私がこれまで仕事をしてきた分野が主です。出版だけでなく、そうした分野の催事(講座、茶会、演奏会など)や、オリジナル商品(器、絵葉書、アクセサリー)の物販も行なっています。
——創刊して1年たちましたが、いかがですか?
面白いです、本作り以外のことは初めての経験なので。以前と比べて「本が売れない」と悩んでいる時間が少なくなりました。もちろんすごく売れているわけではないのですが、やることがたくさんあるんです。いまは自分が動けば動くだけ可能性も広がる気がするので、思いついたらとりあえずやるという感じです。『工芸青花』の8000円という価格は、最終的には勘でした。5000円では原価計算的に厳しい。かといって1万円以上にすることには私自身抵抗を感じました(そうしたほうがいいという意見もありましたが)。1年たってみて、儲かりはしないけれど損もしない、くらいに落ち着いています。
想定する読者とはあくまでイメージにすぎない
——『工芸青花』を作った理由やきっかけを少しずつ伺いたいと思います。これまで菅野さんが仕事をされる中で、今につながるようなことは何かあったのでしょうか?
雑誌の編集部にいた頃は、正直なところ「売ること」についてはあまり考えていませんでした。時代もよかったのだと思います。しかし書籍の部署に異動するとすぐに、これは「売ること」を考えないとまずい、と思い知りました。嫌でも現実(数字)が眼に入ってくるからです。いまにつながるということでは、書籍の部署に移って以降、販促のために著者等のトークイベントを多くやるようになりました。場所も新刊書店に限らず、古書店やギャラリー、カフェなどいろいろです。思いがけず楽しかったのは、来てくれた人たちとの会話でした。編集者は「読者」を想定しがちですが(会議の場で「どんな人が読むの?」と訊かれることも多いですし)、イベントで「本物の読者」に会うと、イメージは所詮イメージにすぎないんだなということがわかりました。
——想定した「読者」のイメージと、生の読者はズレていたということでしょうか?
ズレというか、当り前のことですが、読者はさまざまでした。傾向なんて考えないほうがよいと思いました。例えば若い人は本を読まないという評も、実際に硬軟の本を読破している若者に会うと、いかに紋切型な言葉かと実感します。私が仕事にしてきた美術工芸の分野は、出版界ではニッチです。そうした分野に惹かれる人はそもそも母数が少ないので、老若男女の別に意味はあまりないのです(同志のようなものなので)。トークイベントで「読者」を知り、本は予想外の届き方をする、という実感を抱くことができたのは、いまの仕事に生きていると思います。
——それがわかってから、編集も変わっていきましたか?
はい。「わかりやすく作ること」の呪縛から解放された気がします。これまで例えば美術の入門書なら「初心者にもわかりやすく」と心がけてきました。でも気づいたら、書店の棚にはほとんど同内容の「わかりやすくて親切な」入門書ばかり並ぶようになっていました。それならもう、既にある本と似たような本を自分が作る必要はないだろうと。「わかりやすくは説明できないけれど面白いと思うから伝えたい」という動機で本を作ってもよいのではないかと思うようになりました。なぜなら読者は常に予想外なのだから。本は常に思いがけない受けとめ方をされます。それは言い変えるなら、読者を信頼するということでした。
1分の1の読書体験を目指し、手仕事の器をヒントに
——とんぼの本シリーズを担当されていたのは、2009年から2014年までですね。その間、本離れが進みスマホが浸透して、売上げが低迷した時期でもあると思いますが、現場でも感じられましたか?
ええ。毎年とんぼの本のシリーズ全体の実売部数を営業部に出してもらっていたのですが、よくて現状維持でした。
——そうした厳しい状況の中で『工芸青花』が生まれてきたと思うのですが、どういうきっかけだったのでしょうか?
当然このままでは厳しい、未来は暗いという自覚はありました。でも本の中味・テーマを変えたいとは思いませんでした。背に腹は代えられないという考えのもと、例えばダイエットや英会話や片づけの本を作りたいとは思わなかった。なぜなら「あらゆる本」ではなく「ある種の本」が作りたくてこの仕事をしていたからです。「本」も大事ですが、「ある種の……」のほうが自分にとってはより大事でした。だからまず、これまでのように美術・工芸・建築を取材・編集した本を出し続けるためにはどうすればよいかを考えたのです。中味・コンテンツは変えたくないのなら、仕組みを変えるしかない。とんぼの本シリーズの創刊は1983年です。その理念は、それまで豪華な画集・作品集でしか見ることのできなかった内容を、より多くの人に、手軽なかたちで届けようということでした。それには安価でないといけないので、判型はコンパクトに、造本も簡易に、部数は多く刷る、という仕組みのシリーズでした。
——『工芸青花』とはまったくやり方が異なりますね。
確かに。とんぼの本の創刊理念に逆行していますね。大きな判型、布張り上製本、少部数──このような体裁の本は、とんぼの本の創刊時にはいまよりも多く作られていましたが、残念ながら現在では滅多に作られません。愛蔵版と普及版のどちらかだけより、両方あったほうがいいですよね。本も物なので、たとえ同じ内容でも、文庫本とハードカバーの本で読むのとでは、当り前ですが異なる体験になります。良し悪しではありません。若い頃から骨董・工芸の本が好きで、古本屋で探して買っていました。それらの造本は大判・布張り・ハードカバーが多く、古書でも高価でなかなか買えなかったこともあり、そうした本を手に入れて、時折、本棚から取りだして眺める時間は、いま思いだしてもよいものでした。それは、例えば1杯のコーヒーを飲むときに、どんな器で飲むかによって味は変わらないかも知れないけれど、その間の時間の質は変わる、ということと同じだと思います。おそらく器作家の人たちは、それを信じて器を作っているはずです。