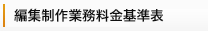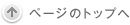拡大編集セミナー2014 第10回 出版の新しい可能性をめざして
出版界の再生 ~まずは編集者よ、元気になろう!
| 開催日: | 2014年10月23日(木) |
|---|---|
| 会 場: | コミュニケーションプラザドットDNP2階 |
| 時 間: | 13:30~17:50(受付開始13:00) |
| 講 師: | 作家 碧野 圭氏 枻出版社 執行役員 埜村 博道氏 (株)コルク 代表取締役 佐渡島庸平氏 |
| 受講者: | 60名 |
第1部 13:30~14:50
『書店ガール』の作者・碧野圭さんが語る書店員の思い、編集者への期待
作家 碧野 圭氏
フリーライター、出版社勤務をへて、作家に転身した青野圭氏。ワーキングマザー編集者の企業内サバイバル小説『辞めない理由』でデビューし、その後執筆した『書店ガール』1~4、は現在23万部を売り上げている。書店に興味がわき、北は盛岡から南は福岡まで書店行脚。のべ130軒以上を自費で回り、本と書店と出版について、貴重な体験談を語っていただいた。
そのひとつのエピソードとして、作家の書店めぐりについて。
「作家が書店まわりをする作家営業は、最近では珍しくないですね。以前は、書店員さんが自らブログに書いてくれたりして、好意的に扱ってくれましたが、最近は、とくに大手の書店さんなどでは、文学賞をとった作家でも『売れたらまたおいで』と言われたり、名刺も受け取ってもらえなかった、などと聞きます。作家や編集者は、傷つきやすく、書店周りも逆効果になったりする傾向がありますから、編集者は営業とよく相談して行かれるのがよいでしょう」とのこと。また、書店員さんの忙しい時間をさける、自分の本の話はあまりしないといった態度が大事とのこと。
出版社と作家と、書店さん三者の協力があってはじめて本が届けられるのですから、三者の協力は大事ということですね。
今は地元愛にめざめて、小説執筆の傍ら、地域雑誌『き・まま』の編集をされている。
受講者とのQアンドAでは、地域紙の編集での質問が相次ぎました。

第2部 15:00~16;20
「得意な分野をことごとく事業化できるのが出版社だ!」
枻(えい)出版社 執行役員 埜邑 博道氏
さまざまなジャンルの雑誌を刊行していて、それに関連するイベント、ウェブ、レストラン、建築……と事業展開して増収増益の枻出版社。その奇跡の事業戦略とはどのようなものか。
2013年に創立40周年を迎え、その年には83億円の売り上げ実績をあげているとのこと。6分間の動画をはさんで、出版を通してのビジネス展開を話していただいた。
年間450冊以上の雑誌・書籍の刊行。そうした出版を基盤にして、さまざまな事業を展開、読者参加型のイベントを数多く展開しているのは、他に例をみない。
たとえば、ファッション雑誌『Lightning』から生まれた最大のイベント「稲妻フェステバル」では約2万人の動員がある。雑誌『RIDERS CLUB』ではサーキットで、会費を35000円払っていただいて、スタッフと一緒になって1日中ライディングを楽しんでいただける。BikeJIN祭りには、4500名超の集客がある。
雑誌や本を、作ったら終わりでなく、この本とずっとつき合っていただきたい。お客さんが離れてしまわないように、いかに余計なことを考えられるか。出版、事業、企画、売り上げ、みなつながっている!
出版社の生き残り、出版不況打開の一つのヒントを熱く語っていただいた。

第3部 16:30~17:50
『出版界の再生をめざして~これからの編集者・出版社の役割』
(株)コルク 代表取締役 佐渡島 庸平氏
講談社に入社し「モーニング」編集部に所属。『ドラゴン桜』『宇宙兄弟』など数々のヒット作を生み出した。2012年、10年間勤務した講談社を退社後、作家のエージェント会社、株式会社コルクを設立。出版界が活気を失っているのは、作品や作家・読者の質が落ちているのではなく、従来のビジネスモデルが時代に対応できなくなったから、と語る。
本を作家と一緒に作り上げることでヒットを生み、実績をあげてきた佐渡島氏だが、コンテンツを作って終わり、という時代ではないことを認識。ネットの時代ならではの可能性、仕組み作りに取り組んでいる。従来のコンテンツの作り方は、人件費を使って、メディアにのせて終わるという仕組みだが、そうではなく、その作品を長期的なコンテンツにするためには、どうすればいいか。コンテンツの価値をどうやって高めるかが大事。そしてコンテンツに再投資することの大切さを、ディズニーやどらゑもんの人気の秘密を例に出して具体的に語る。これからの編集者の仕事は、本を作ることだけではない、情報の順番をコントロールすること、さまざまな場を作ることが求められている。そして『ストーリーを編集する編集者の時代』になる。編集とう仕事はますますなくてはならない時代になる、とわれわれ編集者には、なんとも心強いメッセージをいただきました。