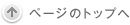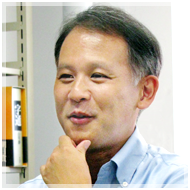
宇野 重規(うのしげき)
1967年生まれ。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。法学博士。
現在は東京大学社会科学研究所教授。専攻は政治思想史、政治哲学。
著書に『デモクラシーを生きる——トクヴィルにおける政治の再発見』(創文社)『トクヴィル 平等と不平等の理論家』(講談社選書メチエ、サントリー学芸賞受賞)などが、共著に『希望学[1]希望を語る —— 社会科学の新たな地平へ』『希望学[4]希望のはじまり —— 流動化する世界で』(東京大学出版会)などがある。
震災を契機に、日本社会の脆弱性が露わになりつつあります。確とした方針を提起できず、その場しのぎの対応に終始する民主党内閣。進行し続けるデフレと円高に苦しめられ、次代の戦略を打ち出せない国内企業。次から次へと変わり続ける教育方針に振り回されながら、未来に対する希望が持てずにいる若者たち。私たちの国は、いったいどこに行こうとしているのでしょうか。 |
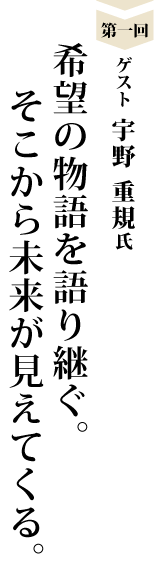
|
| / | |





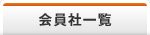

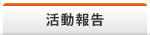
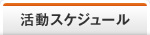
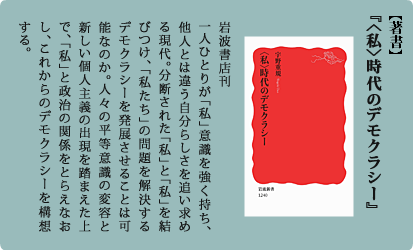 〓
〓